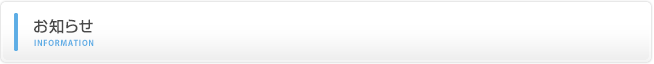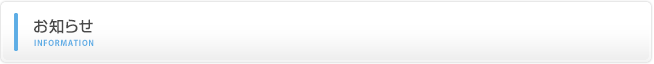
日々勉強(香久山教室)
テスト対策も終わり、束の間の休息と言った時期ですが、ここで甘えてもらってはいけません。
周りがホッと一息つく時間にこそ、差を詰めるチャンスが訪れます。
テスト終わったのに、なんでそんなこと言うの?と言われることもありますが、
ここは心を鬼にして。
日々勉強しなきゃいけないことを伝えていますが、自分がやらない。では
示しがつかないので、自分も資格取得に向けて勉強することを宣言しました。
生徒と同じような分野で勉強するほうが示しがつくかと思ったので、漢検取得を目指します。
みんなが努力するから、先生も努力する。
このスタンスで進んでいきたいと考えています。
2019.10.07 | 香久山教室
習慣と慣習(香久山教室)
塾講師をしていると新しい
ことを学ぶ日々が常です。
今日の授業で、「慣習」という言葉を
見ました。
意味は、「慣れること・ならわし」ですね。
違う文章でも見かけたことがあるので
言葉は知っていましたが、「習慣」と
どう違うんだ?と思い、調べてみると
どちらも「ならわし」ではあるのですが
「慣習」は、社会的な集団・団体に対して
長い年月を経ているもの。
「習慣」は、個人に対して。
使うことが基本みたいです。
※大分簡略化しております。
大人になるにつれ、感覚でなんとなく
そういう違いかな?と思っていたりも
しましたが、改めて調べてみると
はっきりとした違いを認識します。
細かい部分ではありますが、気になった
ことはすぐ調べる。
勉強に関しては、この姿勢が大事だと
思っているので、日々の授業でも
この姿勢を生徒に見せて行くことを
大事にしています。
2019.09.10 | ブログ , 香久山教室
先を見据えた語彙力(香久山教室)
小学生の授業で、国語の文章を一緒に読んでいた時のこと。
「一緒くた」という表現に目が留まりました。
意味は、何もかも(一緒にできないものまで)ひとまとめにすること。同一視すること。です
大人になると、普通に使っている表現の一つではないでしょうか?
いつの間にか知っていた。という方も少なくないと思います。
ただ、小学生にとっては、未知な表現であることが多いのが現実です。
こういった表現を覚えていくことが、後の受験につながったり、
文章を読む力に変わっていくものではあるので、意味がつかめるまでは
先を急がない。この姿勢で小学生をお預かりしております。
2019.09.03 | 香久山教室
解説の重要度(香久山教室)
授業を通して感じること。
問題を解くと、どうしても
正誤だけに意識が向きがちです。
が、間違っていた場合、解説が
重要になります。
※もちろん正解していても重要です。
なぜ、その答えになったのか。
そこを追求して、納得出来なければ
勉強したと言えど、無駄な時間を
過ごしたと言わざるを得ません。
問題を解いた時、どれくらいの
自信で解答したのかも大事ですね。
「2択までは絞れてて、、、
こっちかな?」と思って解答した。
このパターンはダメです!
この曖昧さのまま、同じ問題を
改めて解くと、前回選んだのと
違う選択肢になったりもします。
教材にも依りますが、解説は選択肢ごとに
どこが違うか明記されていたりします。
4択なら、3つは違うことになるので
自信を持って、ここが違う!
と言えるような力を身につけられるよう
解説は必ず読むようにしましょう!
2019.08.20 | 香久山教室
0.999…=1?(香久山教室)
お盆明けで、今日から授業を再開しました!
お盆中も勉強を頑張っていた報告が聞けて、何よりのスタートです♪
1分1秒を大事に使ってほしいので、うれしい限りの報告でした。
さて、授業が再開したので、勉強の内容を書きましょう。
タイトルの式ですが、正しいでしょうか???
答えは
↓
↓
↓
「数学的には正しい」です。
ん?
どういうことだ?
となりますよね(笑)
証明方法は割愛しますが、限りなく近づける(高校数学でいうところの極限lim)
を使うと数式的に正しいと証明できる問題になります。
ただ、あくまで数式的に等しいとは言えますが、実際の数字として=ではないということ。
ここが肝です。例えば、左手にはリンゴを1つ、右手には0.999…つのリンゴを持っている。
右手側のリンゴは数えようとしても、永遠に9が続くので、終わりがありませんよね?
1つ、と数えきることのできない0.999…つ。
同じではないことが誰の目にも明らかです。
ではなんでこんな現象が起こるか?
これは、高校数学のlimの関数が持つ曖昧さだと思うのですが、
limの式は、限り無く近づけると、いずれそうなるという等式なので、
目には=という記号が飛び込んできますが、現実には、→の意味合いなのです。
タイトルの式に戻ると、0.999…=1と数学的には表せますが、
0.999…→1なのです。
自分が一番納得した表現は、0.999…の9を続けていけば
限り無く1に近づくというものですかね。
あくまで、限り無く(無限)続けることが重要になります。
式としては=として表記できるけど、実際に等しいわけではない。
といったところが、落としどころでしょうか。
すんなり腹落ちしづらいものだとは思いますが、こういった疑問を
納得できるまで調べてみる。これも勉強ですね。
久しぶりに、高校数学の知識を要する問題に触れて楽しかった(笑)
2019.08.19 | 香久山教室
時には遠回り(香久山教室)
授業を通して感じることですが、興味が湧くと勉強へのノリが違います。
社会はその傾向が強いですね。男の子が特に(笑)
過去の人物には、実はこの説がある。とか、あの人はいなかったんじゃないか。とか
例)・豊臣秀吉のあだ名は「サル」以外に「はげねずみ」があった。
↓
織田信長が、秀吉の正室である寧々へ送った手紙にその記載がある。
・源義経=チンギス・ハンであった。
↓
年代・背格好が同じ
源義経は「九郎義経」という別名があり、チンギス・ハンにも「クロー」という別名があった。
代表的なところで言うと上の例ですかね。※諸説あり
挙げだしたらキリがないことも事実ですが、選び取った情報で、「へぇ~、そうなんだ!」と
なったら儲けものです。実は、この「へぇ~」が意外なほど、忘れない知識になってることが多いのです。
教科書から多少脱線してしまう部分もありますが、遠回りをした方が、意外と楽しく覚えられたり、
重要事項と紐づいて忘れなかったりすることも多々あります。
ただ単調に、これはあれ。とか、それは誰々。とか機械的な覚え方をするのが、
苦手な子にとって、そういった道も示していきたいですね。
教科書に沿った指導もしますが、勉強意欲のきっかけになればと思い、日頃の指導に活かしています。
そのためにも、細かな予備知識を増やしていきたいですね!
今後も活かせそうなものは日頃から吸収して、伝えていきます!
2019.08.08 | 香久山教室
課題は早めに(香久山教室)
夏休み。ということで、学生の皆は学校の課題がたくさんあるかと思います。
そんな中、全部ではないですが、8・9割課題を終わらした生徒もちらほら。
いやぁ、尊敬しますね!
自分は決して、ため込むタイプではありませんでしたが、ここまで早かった
記憶はありません(・・;)
勉強への意識が高くて何よりです♪
課題=最低限の勉強なので、周りと差をつけるために、+αを望むなら、早めにこなすが吉ですから。
使える時間が多くなる→自分の苦手を潰せる→受験の傾向に寄せた問題も取り組める。
良い事尽くしですよね!
あとは、学んだことをその場限りの知識にしないよう、何度も解くことですね!
勉強に関しては、一度納得してしまえば大丈夫!となりやすいので、
そのアプローチはしっかりかけていきます!
一度解けたものは、半永久的に解けるようにさせる!
を目標に夏期講習を進めてまいります。
2019.07.29 | 香久山教室
伝わるように組み立てる(香久山教室)
香久山教室の志治です。
長久手教室のTwitterに関するブログで、「生徒に教えを乞う」的な記載がありましたね。
この立場の逆転、僕は推奨派です。
教わる側が、教える側に転じること。
教える側が、教わる側に転じること。
どうすれば伝わるのか?を考えてもらう良い機会になりますよね!
そのネタが現代の子たちの得意分野だったりするのも良いですね。
おそらく、教えを乞うと前のめりになって教えてくれることでしょう。
自分の得意なものほど相手に話したくなる要素を多く含んでいるので。
相手が僕ら講師というのも大きな要因ですね。
友達同士だと、分かり合える幅が広いというのでしょうか?
多少説明が省略されていても伝わるでしょう。
でも、一定の距離がある相手に、自分の思いを伝えようとすると、そう簡単ではないですよね?
この相手に伝えるために、話をどう組み立てるか?
これを意識してもらうだけでも非常に大きな意味を持つと思います。
自分が率先して受け身になることで、生徒のそうした力も高めていけたらと思います。
もちろん僕自身も、日々の授業に関して、伝わるような話し方を工夫していきます。
2019.07.12 | 香久山教室
暗記のコツ⑦(香久山教室)
香久山教室の堀です。
いよいよ、テストが始まりましたね!
最後の最後まで基礎の確認を徹底しましょう!
テスト問題は、まず全体を把握してから解きましょうね!
さて、本日は暗記のコツ⑦です。
ずばり、暗記のコツ⑦は、、、
こまめに暗記補給をする
です。
暗記のコツを説明するときは、
理解しやすいように単語だけや社会の用語だけで説明してますが、
リアルな勉強は、複数教科を勉強しなければいけません。
これがなかなかやっかいです。
「記憶のキープ」が意識できていない子は、
一日中ずーっと数学のワークを20ページくらいやり続け、
次の日は一日中ずーっと理科のワークを20ページくらいやり続けます。
その間に暗記のコンボが途切れ、漢字や英単語や社会の用語を忘れてしまうのです。
コンボとは、英語のコンビネーション・ボーナス(Combination Bonus)を略した語であり、ビデオゲームにおいて手の一種、もしくは何らかの意味を持つプレイヤーの連続行動のことを表す用語である。(※Wikipediaより引用)
【イメージ図】
<暗記コンボなし勉強>
暗記①→ワーク20ページ→(コンボ切れる)→暗記①→ワーク20ページ→(コンボ切れる)→暗記①
※コンボ記録:暗記コンボ①
<暗記コンボあり勉強>
暗記①→ワーク5ページ→暗記②→ワーク5ページ→暗記③→ワーク5ページ→暗記④→ワーク5ページ→暗記⑤
※コンボ記録:暗記コンボ⑤!
このように暗記コンボを切らさないように意識して勉強してみてください。
暗記①で何を勉強したらいいか、暗記②で何を勉強したらいいか、など
詳しく書きたいのですが、それはまたの機会に。
今まであまりコンボを意識していなかった方は、
こまめに暗記補給をしてコンボを築くようにしてみてください!
ではでは!
2019.06.20 | ブログ , 香久山教室
百里を行く者は九十を半ばとす(香久山教室)
香久山教室の志治です。
「百里を行く者は九十を半ばとす」ですが、
何事も、後半が困難であるから、九分どおりまで来てやっと半分。
と心得て、最後まで気をゆるめるな、という戒めの言葉です。
このような故事成語も、日々の勉強の中で覚えてもらいたいと思う今日この頃です。
さて、タイトルに選んだ理由ですが、
生徒が今日も仕上がりを意識しながら、勉強に励む姿勢を見て決めました。
生徒を見ていると、姿勢が物語っているので、安心させてくれます。
一部の子が、今日からテストですが、明日明後日もテストがあるので、
この姿勢を保ちながら、乗り切ってほしいな、と思います。
短めですが、今回はこの辺で。
2019.06.17 | 香久山教室